IoT
-

ESP32(Arduino)で SigFox をはじめるまで
-

ダイソーのリモコンシャッターをESP32で通信するためのヘルパー関数
-

ダイソーのBluetoothリモコンシャッターをESP32でハックする
-
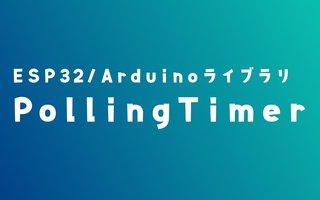
ESP32(Arduino)で擬似マルチスレッド可能な「PollingTimer」ライブラリ開発のリリースノート
-

ESP32でHTTPSアクセス、ただし証明書検証なし
-

ESP32のマルチスレッドで複数のサーボモータを同時に動かす方法
-

ESP32でBluetooth Classicを使ってAndroidと通信する
-

Clion x PlatformIOでESP32(Arduino)開発
-

Arduino Uno R3、R4、Pico W、ESP32のスペック性能比較してみた
-

Arduino Unoで内蔵メモリEEPROMを使って状態を保存する方法
-

物理ボタンを付けてRaspberry Piを安全にシャットダウンする方法
-
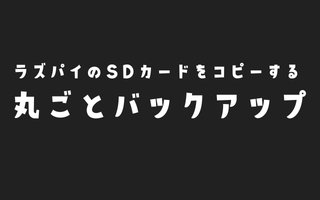
Raspberry PiのSDカードを丸ごとコピーしてバックアップする方法、やり方
-

Raspberry Pi OS Lite (64Bit)をRaspberry Pi 4へインストール
-

ADコンバータADS1115の使い方【ESP32・Arduino】
-

自作LANケーブルの作り方〜Arduinoとセンサ間をLANケーブルでI2C、1-Wire、電源供給
-
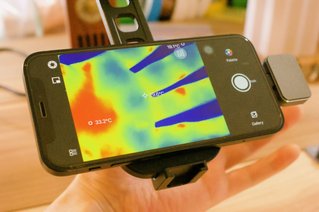
iPhoneやAndroidで使える!サーマルカメラ「InfiRay Xinfrared P2 Pro」のレビュー
-

ESP32でMOSFETを使ったPWM制御 (IRF520)
-
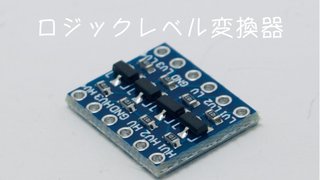
ロジックレベル変換モジュールの使い方|Arduino・ESP32・ラズパイ
-

DS18B20の使い方|Arduino・ESP32・Raspberry Pi
-

電磁弁とESP32で水道のオンオフを制御してみた
-

昇圧型DC-DCコンバータでESP32の5Vから12V電源をつくる(MT3608)
-

ESP32へ書き込みエラー・MacBook 2022でconnectできない・自動書き込みに失敗したときの解決方法
-

ESP32でAdafruit STEMMA Soil Sensorを使って土壌水分量と温度の測定
-

ESP32で照度センサTSL25721を使ってみた
-

ESP32でST7735 TFT LCD液晶ディスプレイを使ってみる
-

ArduinoでTFT LCDディスプレイ(ST7789)を使ってみる
-

Arduino Unoのシールド基板で、アナログセンサのデバッガーを作ってみた
-
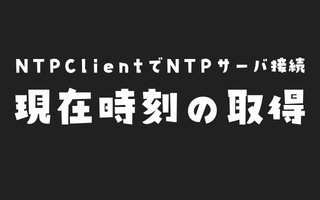
ESP32でNTPClientライブラリを使って現在時刻を取得する方法
-
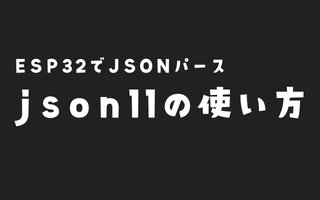
ESP32でjson11を使ってJSONを簡単に扱う方法|JSON文字列のパース|配列をJSONに変換
-

ESP32でHTTPClientを使ってウェブサーバーにGET、POSTするやり方
-

【Arduino開発】Platform IOでdebug版、release版を分けてビルドして実機へアップロードする方法
-

Arduinoでできること
-

Raspberry Piでできること7選
-

【Python】OpenCVで画像をアフィン変換【移動・拡大・回転・剪断】
-
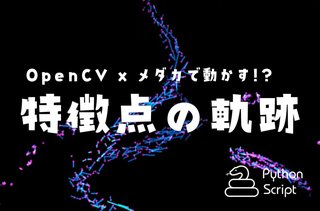
【Python】OpenCVで特徴点の追跡【メダカの軌跡】
-

【Python】OpenCVで図形の描画からアニメーションまで【線・四角・丸・塗りつぶし】
-

【Python】OpenCVでコーナーの検出【Harris/Shi-Tomasi】
-

【Python】VidStabで手ぶれ補正【動画編集への道#2】
-

【Python】MoviePyで動画編集の自動化【動画編集への道#1】
-

【Python】OpenCVで画像操作いろいろ(グレースケール・モノ・輪郭抽出・切り抜く・透過)
-

【tesseractでOCR】PDFから文字の抽出→文字データが埋め込まれたPDFを作成【自炊への道】
-
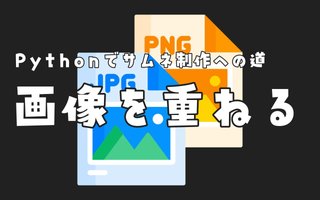
【Pythonでサムネ制作②】PILで画像の上に透過画像を重ねる
-

【シェル】waifu2xで劣化した写真や画像を高画質化【macOS】
-

【Raspberry Piではじめるnginx②】リバースプロキシとPythonのFlaskで爆速!API制作
-

【Raspberry Piではじめるnginx①】nginxをインストールしてHTMLを表示させるまで
-
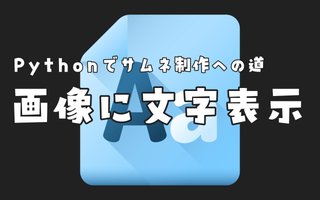
【Pythonでサムネ制作①】PILで画像の上に文字を重ねて中央表示
-
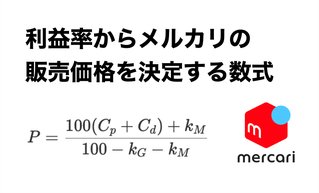
【数学】利益率からメルカリの販売価格を決定できる数式をつくるよ!
-

ESP32とMH-Z19CセンサでCO2濃度の測定
-

【XYペンプロッター制作⑧】必要な部品、おすすめパーツのまとめ
-
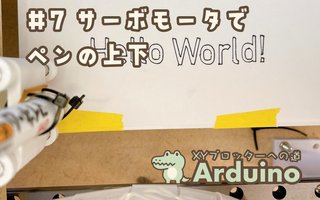
【XYペンプロッター制作⑦】サーボモータでペンを上下させる(仮完成)
-
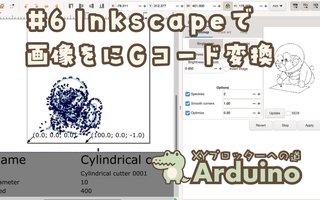
【XYペンプロッター制作⑥】Inkscapeで画像をGコードに変換する
-

【XYペンプロッター制作⑤】リミットスイッチでホーミング
-

【XYペンプロッター制作③】CNCシールドの設定「マイクロステップ分解能」
-
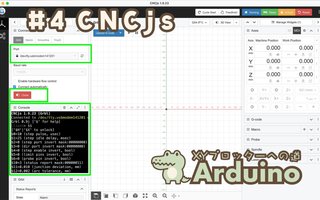
【XYペンプロッター制作④】Grbl v0.9とCNCjsのインストール
-
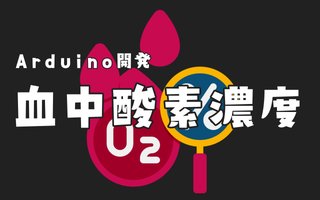
【Arduino】MAX30100で心拍数と血中酸素濃度の測定【パルスオキシメーター】
-

【XYペンプロッター制作②】リニアガイドとタイミングベルトで直線運動
-

【XYペンプロッター制作①】CNCシールドでステッピングモータを動かすまで
-

ArduinoからATtiny85へ書き込んでLチカする
-
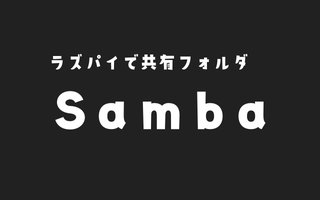
【Raspberry Pi】Sambaで共有フォルダをつくるまで
-

ArduinoでマイクロSDカード〜書き込み読み込み記録する
-

【Arduino】リアルタイムクロック(DS3231)で現在時刻の表示
-

Raspberry PiとOctoPiで3DプリンタをWiFi化してみた〜WEBブラウザから印刷するまで
-
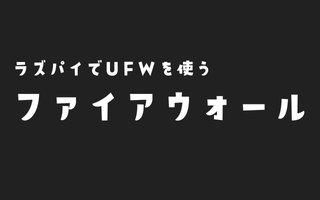
【Raspberry Pi】ufwでファイアウォールの設定
-

ArduinoでLCDに文字表示
-

Arduinoとサーミスタで温度測定
-

そうだ!Arduinoでヨーグルトメーカーをつくろう!
-
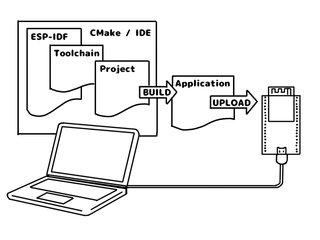
ESP-IDFでESP32の開発をはじめよう!
-

おすすめArduinoどれを選べばいい?Arduinoで電子工作をはじめる方へ
-

M5StickC PLUS BLACK!?黒くぬれ!
-

はじめてのBLE通信、iOSからESP32のLチカ
-

ESP32でBLE通信、ESP32からiOSでデータ受信
-
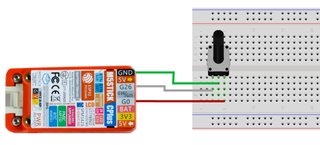
M5StickC PLUSとロータリーエンコーダ
-

ESP32でジョイスティックを使ってみよう【Arduino】
-

ESP32でESP-NOWを使って通信してみよう
-

SonyのデジイチをM5StickC PLUSでリモート操作できるようにしてみた
-

ArduinoでC++で作った自作ライブラリを使う方法
-

においセンサ(TGS2450)で匂いを数値化するArduinoプロジェクト、基板も作ったよ
-

M5StickC PLUSの内蔵ADコンバータで電圧測定
-
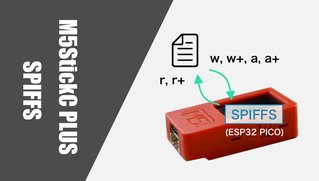
ESP32でSPIFFS領域に保存する方法【M5StickC PLUS】
-

M5StickC PLUSの加速度センサで振動測定と周波数特性
-

M5StickC PLUSで画像を表示してみた
-

M5StickC PLUSでArduinoをはじめよう!
-

ラズパイからRTMPでライブ配信(ニコ生)
-

テザリング環境でRaspberry PiをSSH操作
-
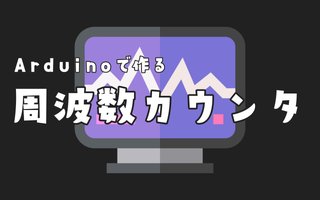
Seeeduino Xiaoで周波数カウンタをつくろう【Arduino】
-

Arduinoで可変電圧器【Seeeduino Xiao】
-
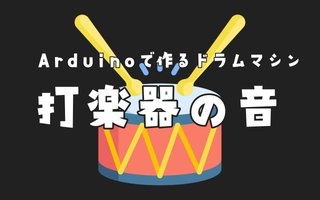
【Arduino】打楽器の音色をつくってみた【ドラムマシン】
-
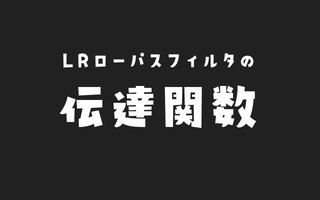
LRローパスフィルタの伝達関数
-

Arduinoでステッピングモータの制御|ユニポーラ型「28BYJ-48」と「ULN2003」ドライバ
-

Arduinoと可変抵抗でLEDの明るさ制御
-

ArduinoとCdS光センサ
-
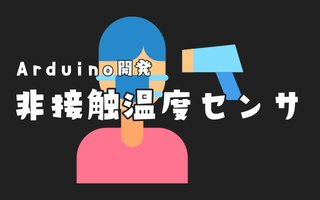
【Arduino】非接触温度センサ(GY-906)をつかってみた
-

伝達関数から周波数応答(周波数振幅特性と周波数位相特性)
-
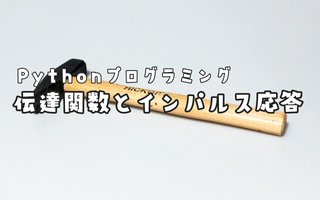
伝達関数とインパルス応答
-
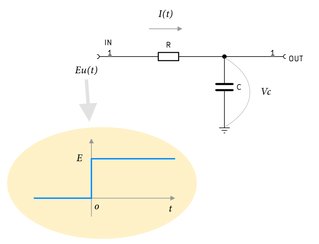
RCローパスフィルタのステップ応答
-

はじめてのラプラス変換
-
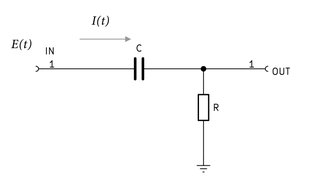
デジタル信号におけるRCハイパスフィルタ
-
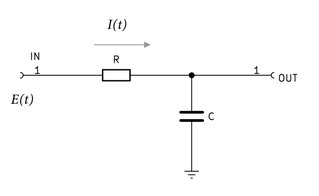
デジタル信号におけるRCローパスフィルタ
-

加速度センサで角度の計算|ArduinoとMMA8452Q
-

Arduinoでコンデンサの静電容量測定
-
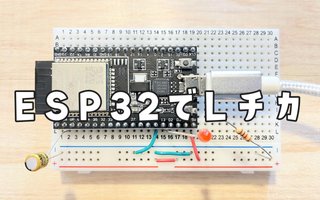
ESP32でLチカするまでの設定
-

Pro Microと静電容量式タッチセンサ(TTP223)【Arduino】
-

Arduinoと抵抗で作る自作タッチセンサ〜Pro Micro編
-

Pro MicroでArduinoをはじめよう!〜Lチカするまで
-

【Raspberry Pi】ステップ応答による抵抗値の測定
-

Visual Studio CodeでArduino開発をはじめよう
-
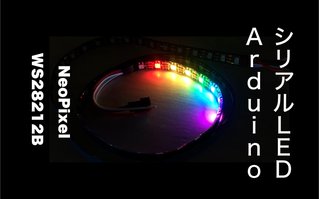
ArduinoとシリアルLED(WS2812B)
-
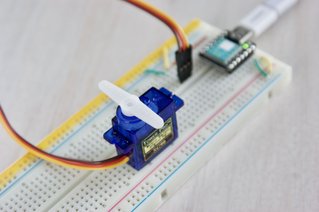
ArduinoでマイクロサーボモータSG90の使い方
-

Raspberry PiでOLEDに文字表示
-

【Raspberry Pi】spi.xfer2関数の使い方を徹底解説
-

【Raspberry Pi】Ambientへセンサデータを送信してグラフ化
-
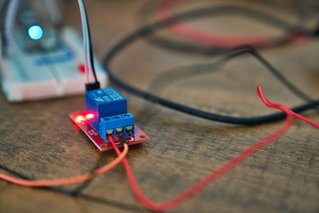
リレーモジュールの使い方|Raspberry Pi・Arduino(ESP32)
-

【Raspberry Pi】ADコンバータMCP3425の使い方
-
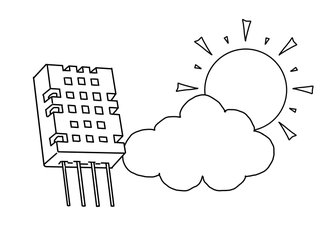
温度湿度センサDHT11・DHT22をArduino・ESP32・ラズパイで使う
-

超音波センサHC-SR04の使い方|ArduinoとRaspberry Piで解説
-

【Arduino】OLEDに文字表示【Seeeduino】
-

Seeeduino XIAOでArduino開発をはじめよう
-

Raspberry PiでMOSFETを使おう
-

【Raspberry Pi】FFmpegでHLS配信ライブストリーミング
-

【Raspberry Pi】GStreamerでHLS配信ライブストリーミング
-
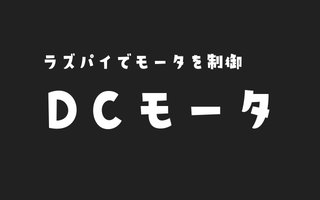
【Raspberry Pi】モータドライバTA8428Kでモータ制御
-

【Raspberry Pi】ECMで音センサつくってみた
-
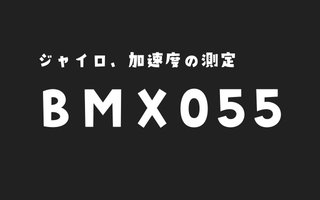
【Raspberry Pi】BMX055でジャイロ・加速度の測定
-

【Raspberry Pi】ADコンバータMCP3008の使い方【SPI通信】
-

静電容量型の土壌湿度センサを使ってArduinoで土の水分量測定
-

【Raspberry Pi】照度センサ(フォトトランジスタ)と温度センサ(TMP36)
-
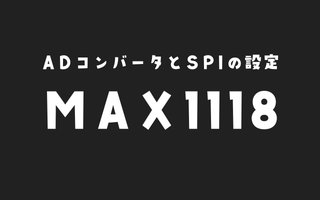
Raspberry PiでSPI通信できるようにする設定【ADコンバータMAX1118】
-

Raspberry PiでWebSocket|Lチカ、WebSocketの理解
-

Raspberry Piでカメラモジュールの使い方【コマ抜き撮影】
-
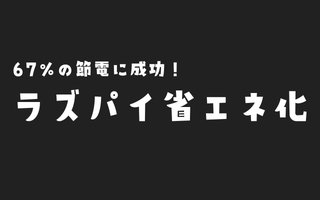
Raspberry Piの省エネ化
-
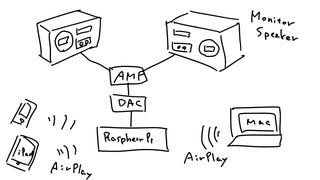
Raspberry PiをAirPlay化して無線オーディオ
-

Raspberry Piでステッピングモータの制御
-

10日で作る!ラズパイ倒立振子ロボット
-

フーリエ変換を理解するまでの数学的メモ
-
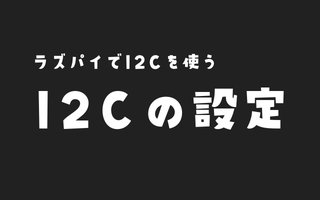
【Raspberry Pi】はじめてのI2C設定
-

Raspberry Pi zero WHをモニター・キーボードなしでSSH接続するまで
-

ESP8266でWiFi通信【ESP-WROOM-02・Arduino】
